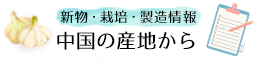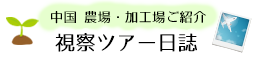コラム
港湾ストライキ
2025年5月1日
4月13日(日)、20日(日)、27日(日)と毎週日曜日の朝から翌月曜日の朝にかけての24時間、港湾でストライキが決行されました。5月も同様に、11日(日)、18日(日)に24時間のストライキをおこなうと通告されていていて、11日(日)は決行することが既に表明されています。
このようなストライキが実施されるのは6年振りとのことです。
弊社では、港湾ストライキの影響で、市場のお客様が月曜日に販売するために、いつも日曜日に出荷している生鮮野菜が出せなくなってしまうため、前倒しして土曜日に納品するといった対応をとっています。そのため、正直なところ、なんとも厄介で迷惑な印象を持ってしまいましたが、それは港湾事業とそれを担う方々の苦労を理解していないが故でした・・・
ということで調べてみました。
港湾ストライキとは、「全国港湾労働組合連合会」略して”全国港湾”と「全日本港湾運輸騒動組合同盟」略して”港湾同盟”が合同で、賃金の値上げ等を求め荷役を拒否(つまりストライキ)することです。
(以下、2025年4月15日「港湾ストライキの実施と背景について」港湾労組記者資料より)
港湾運送事業とは、港湾において、海上輸送される貨物を積載した船舶の船積・卸と、その前後で行う倉庫やターミナルでの荷捌き、貨物量の証明(数・重量・容量など)を行う事業で、国土交通省に許可を受けた民間事業者とそこに雇用された労働者が担っています。四方を海に囲まれている日本では、輸出入貨物の99.6%が海上輸送で、港湾労働者の手を経ています。
【港湾事業・労働者の問題点】
・ 港湾/運送はユーザーのオーダーにより業務が発生し、その料金はユーザー優位で設定される傾向があります。
・ 船舶の運航や寄港及び貨物の発着は極めて流動的で、土日出勤や平日深夜、酷い場合は徹夜での労働が常態化しています。
・ 基本的に屋外で、酷暑や極寒の厳しい労働環境の中、危険性の高い仕事をする必要があります。
・ それらが故に、就職希望者が少なく、離職者は増える一方で、人員不足が深刻化しています。
このような作業労働時間、賃金、休日休暇、安全をはじめとする、最低限の基本的労働条件を見直したいということで、今回のストライキを実施するに至っています。
この資料を読んで、支えられている輸入卸業者として(個人的にはわずか限られた経験しかないながらも)、港湾運送事業及びその従事者の方々にかかってきた負担の大きさや厳しさは想像以上だということを思い知りました。(こんな書き方をしては本当に失礼かと存じますが)俗に言う「ブラック」な業態は、私達ユーザー側の都合を優先してきた結果だということも、今更ながら改めて認識されました。そして、「労働時間短縮」「労働環境整備」「賃金アップ」など、少しでも適切なものとなって欲しいと思うに至りました。
とはいえ、受益者として、港湾・運送料金の値上げは抵抗が大きく、一筋縄にはいかないこともわかります。2024年に運送業界に大きな改革があったように、港湾事業にも大きな改革が必要であり、そのためには国が政策として体制を整えていく必要があると思われますが、現状として政府の施策は望ましい方向性ではないようで、今回のストライキが長期化している要因は、この問題の大きさと深さ、そして働く人達がもう限界を超えた危機的状況にあるからだと納得せざるを得ません。