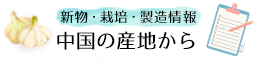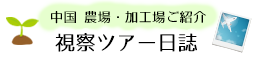コラム
食料システム法について
2025年11月19日
「食料システム法」とは?
いつのまにやら・・・という印象で、食品に関する新たな法律が制定されていました。「食料システム法」です。
「食料システム法」は通称で、正式には「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」という長い名前がついた法律です。
詳細は、農林水産省HPの概要パンフレット上に公表されていますが、自分なりに理解した内容をまとめてみます。
この法律は、簡単に言うと、
・ 食品のサプライチェーン全体で適正な取引を行うこと、
・ 持続可能な食料供給体制を確立すること、
を主な目的として制定されたもので、2025年6月に公布、2026年4月から全面施行の予定だそうです。
「食料システム」とは?
そもそも「食料システム」という言葉自体、これまで聞いたことも使ったこともありませんでしたが、
「食料システム」とは、
「調達から生産、加工、流通、消費まで、食に関わるあらゆる関係者の つながりを1つの大きな仕組みとして捉えたもの」だそうです。
ということは、食品卸業者である弊社は、まぎれもなく「食料システム」の一員ということになります。
では、「食料システム」に関わる一員として、この法律はどのような影響をもたらすでしょうか?
「法律が生まれた背景」
この法律が出来た背景には、近年の原材料費や人件費といったコスト全般の高騰、そして食品業界を取り巻く環境の変化があります。
それなら確かに、自分達にも大いに身に覚えがあります。
例えば、原価の上昇に加え、輸送費や保管料なども断続的に高騰し、負担はますます重くなっています。
そして、それに伴い、赤字とならない適正な利益を確保するために、価格交渉が繰り返し必要となります。
しかし、値上げを快く受け入れてくださるお客様は少なく、交渉が難航することも多々あります。
断られたり、先延ばしにされたりする中で、競合他社に顧客を奪われたり、在庫が売れ残ることを恐れて、
やむなく赤字を受け入れざるを得ない状況も少なくありません。
「法律が求める2つの努力」
この法律では事業者に対し2つの努力を促しています。
1.取引の適正化 :
食品のコスト割れを抑止するため、適正な取引をする努力義務が課されます。
・ 農林水産大臣が「行動規範となる判断基準」を定め、指導・助言などの措置を講じます。
・ 指定された品目については、コスト指標が定められます。
2 計画認定制度 :
持続可能な食品供給のための取組みを評価・認定し、融資など支援措置が講じられます。
取り組みの例 :
・ (農林水産物)生産者への協力活動
・ 労働生産性向上につながる流通の合理化
・ 食品ロス削減など環境負荷を低減する活動
・ 消費者に対する情報提供(継続可能性やコスト構造など)
「今後の展望」
定義としては、“いまどき”という印象はあるものの、具体的な「行動規範となる判断基準」などがまだ示されていないこともあり、現時点では曖昧模糊とした法律だなと感じています。
これが、商慣習に大鉈を入れることになるのか、あるいは絵に描いた餅的な理想論で終わってしまうのかは、まだわかりません。
生産者や加工業者、小売業者、そして消費者まで、すべてが「食料システム」の関係者であり、立場によって受ける影響は異なりますし、受け止め方や感じ方も十人十色でしょう。
ただ、商売の利害関係は複雑で、一筋縄ではいかないことは明らかなので、果たして実効性をもつのか、正直不安も感じます。
それでも、こうした課題へ踏み込もうとする姿勢には、ひとかたならぬ決意が秘められているように思われ、個人的には期待を寄せております。
ちなみにこの10月、農林水産省が食品関連事業者に対しアンケートを実施しました。
主な質問は「コスト上昇の状況」「価格交渉・転嫁の状況」「負担となる商習慣」「価格交渉の良悪事例」で、弊社もアンケートに回答しましたが、かなり細かく具体例を求められる内容でした。
同業他社はもちろん、様々な立場の回答結果すべてに、この法律の行方を左右するヒントがあるものと注目しています。